都立高校入試(共通問題)国語では、大問4の最後で二百字以内の作文が出題されます。たとえば、令和6年度の問題は次の通りです。
国語の授業でこの文章を読んだ後、「互いの思いを一致させること」というテーマで自分の意見を発表することになった。このときにあなたが話す言葉を具体的な体験や見聞も含めて二百字以内で書け。
多くの都立高校受験生がこのような作文を苦手とします。しかし、都立高校入試(共通問題)国語の作文は、実はとても簡単に対策できて、得点源にすることすら可能です。
今回は、入試本番直前でも間に合う作文対策を紹介します。コツさえ掴めば、誰でも確実に10点を得点できます。
※続きはnoteでお読みいただけます。
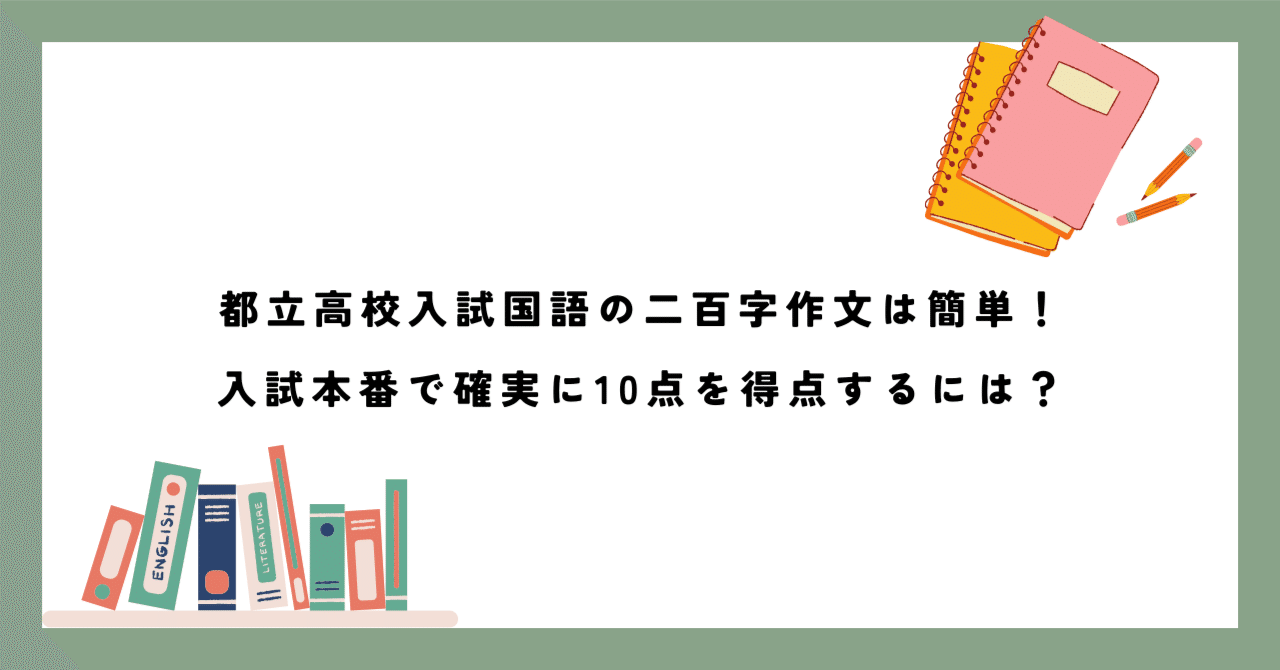
都立高校入試国語の二百字作文は簡単に書ける!入試本番で確実に10点を得点するには?|みみずく|家庭教師&ライター
都立高校入試(共通問題)国語では、大問4の最後で二百字以内の作文が出題されます。たとえば、令和6年度の問題は次の通りです。 国語の授業でこの文章を読んだ後、「互いの思いを一致させること」というテーマで自分の意見を発表することになった。この...



コメント