小中学生の夏休みの宿題に短歌や俳句があります。一般社団法人倫理研究所主催「しきなみ子供短歌コンクール」などに応募するための作品を作ることが求められます。
短歌は五七五七七の三十一字、俳句は五七五の十七字です。文字数が少ない分、読書感想文や人権作文などより楽そうです。しかし、子供たちは「何をどう書けばいいのかわからない」と悩みます。保護者も子供に適切なアドバイスができずに困ります。
そんな子供と保護者のために短歌や俳句の作り方を紹介します。当記事の3STEPに従えば、誰でも簡単に短歌や俳句を作れます。
※続きはnoteでお読みいただけます。
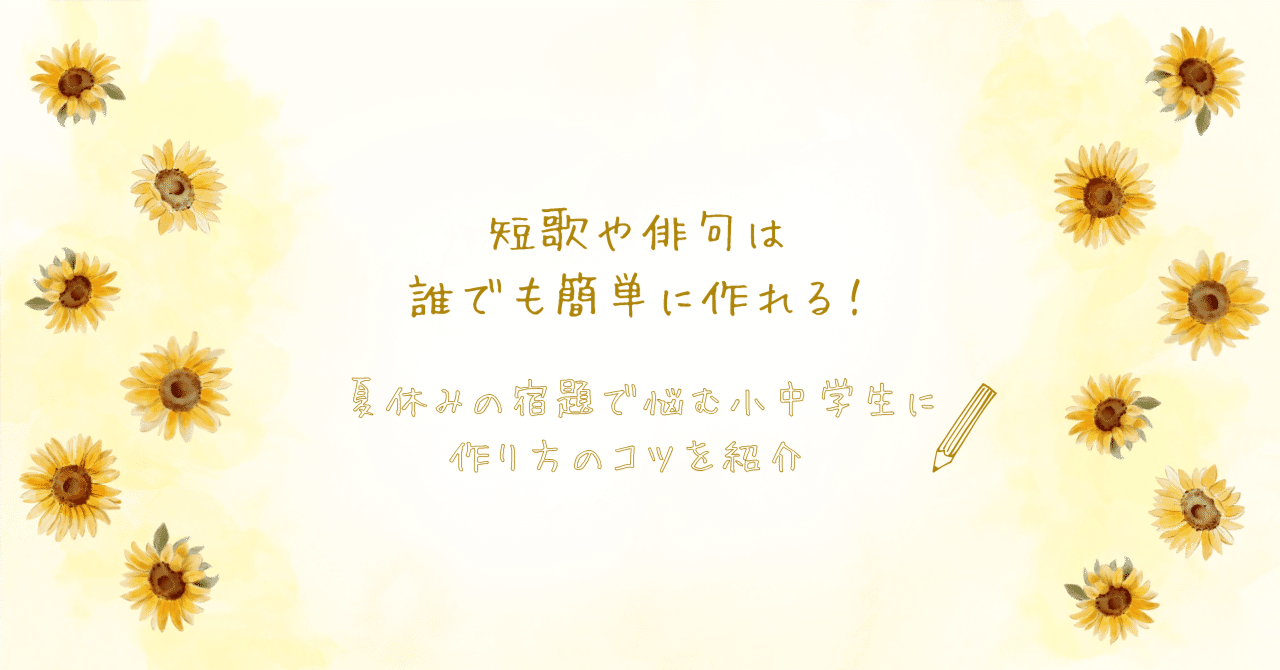
短歌や俳句は誰でも簡単に作れる!夏休みの宿題で悩む小中学生に作り方のコツを紹介|みみずく|家庭教師&ライター
小中学生の夏休みの宿題に短歌や俳句があります。一般社団法人倫理研究所主催「しきなみ子供短歌コンクール」などに応募するための作品を作ることが求められます。 短歌は五七五七七の三十一字、俳句は五七五の十七字です。文字数が少ない分、読書感想文や...



コメント
ありがとう